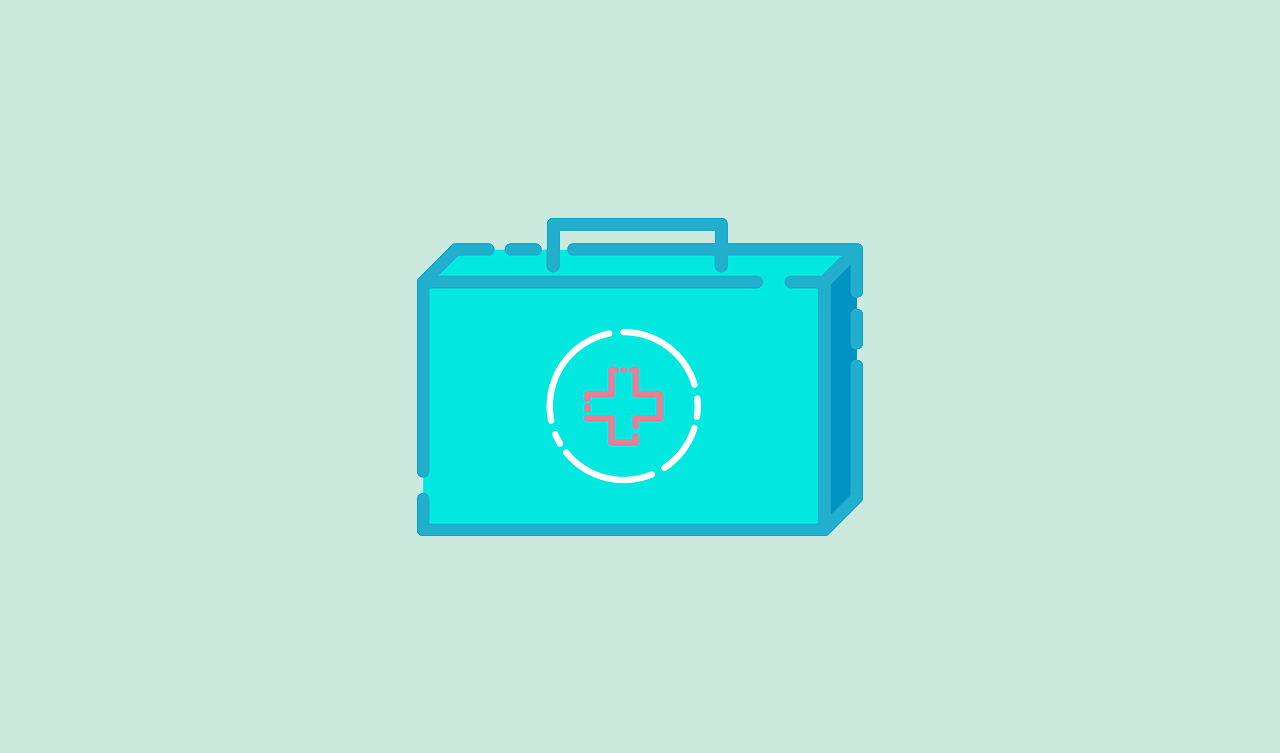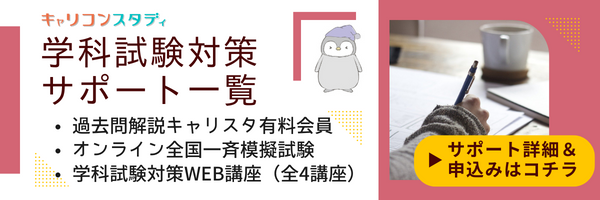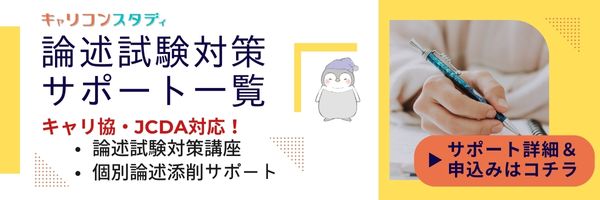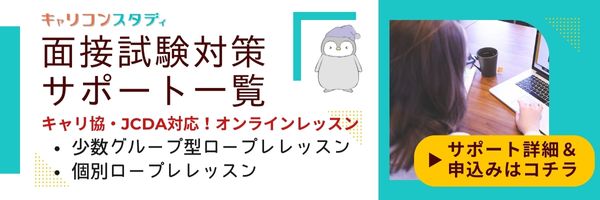産前産後・育児に関する問題は頻出で、保険や法令と範囲も広く数字も多いのでなかなか覚えるのに苦労するジャンルではないかと思います。
僕自身も、学科試験の対策の際に最後まで苦手問題として残ったジャンルでもあります。
本記事では、そんな産前産後・育児に関する関連するポイントを過去問の傾向からまとめています。
厚生年金
産前産後休業・育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が申出をすることによって、その間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
国民年金と厚生年金の違いなどをまとめた記事が下記になります。比較表もありますので、参考にして下さい。

健康保険
子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。この出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に申請されると1児につき50万円が支給されます。(健康保険法施行令の改正(令和5年4月1日施行)により42万円から50万円に引き上げられました。)
出産のため会社を休んだときは出産手当金が支給されます。被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
また産前産後休業期間については、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除されます
健康保険に関してその他のポイントも含めて、まとめた記事が下記になります。

雇用保険料
育児休業給付や介護休業給付などは、雇用保険の被保険者であれば、ハローワークで申請することで支給を受けることができます。
また雇用保険料については、産前産後休業中、育児休業中、介護休業中に賃金が発生した場合は保険料の負担があるので覚えておきましょう。
その他の雇用保険に関するポイントをまとめた記事は下記になりますので、そちらの学習がまだの方はチェックしておいてください。

育児・介護休業法
育児・介護休業法による育児休業をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者になります。有期契約労働者も1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない場合は対象となっています。
子が1歳に達する時点で保育所に入れない等の場合には、申し出により、育児休業期間を子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長できます。
主に男性の育児休業取得促進のための産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間まで、育休とは別に取得可能となります。
また、パパ・ママ育休プラスという、両親がともに育児休業を取得する場合に、一定要件を満たせば、休業可能期間が、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2か月になるまでに延長される制度があります。
労働者は、休業開始予定日の1か月前までに、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に申出ることが要件となっています。
所定外労働の制限・時短措置・子の看護等休暇
所定外労働の制限(残業免除)について対象が拡大され、3歳未満から小学校就学前の子を養育する労働者となりました。(令和7年4月1日改正)
時短措置は小学校までの子ではなく「3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない。」とされています。
また、テレワークも選択できるように措置を講ずることが努力義務化されました。(令和7年4月1日改正)
子の看護等休暇は労働者に付与することが義務付けられている点も要チェックです。
育児・介護休業法について、改正されたポイントも含めまとめた記事が下記になりますので確認しておいて下さい。

まとめ
まとめてみると、それほどボリュームがあるわけではないことが分かりました。
ポイントをしっかり掴んで、得点源につなげていただければ幸いです。
また、関連する練習問題を下記記事にまとめていますのでチャレンジしてみて下さい。