これまでの過去問で出題されていた「健康づくりのための睡眠指針2014」が見直されました。新たに2024年2月に策定、公表された「健康づくりのための睡眠ガイド2023」に関する◯✕練習問題になります。
本記事の問題はキャリアコンサルタントの試験対策用に作っていますので、
- 全過去問の傾向
- 健康づくりのための睡眠ガイド
を主に参考にしているのと、問は随時追加していこうと思っています。
では◯✕練習問題スタートです。
健康づくりのための睡眠ガイド2023の試験対策◯✕練習問題
問1
◯:7時間前後より長い睡眠も短い睡眠も、これらのリスクを増加させることが報告されている。
問2
✕:加齢により徐々に短くなる。25歳で約7時間、45歳では約6.5時間、65歳では約6時間というように、成人後は20年ごとに30分程度の割合で夜間の睡眠時間が次第に減少する。
問3
◯:アルコールと睡眠の関係の説明として正しい。
問4
◯:睡眠の質を高める説明として正しい。
問5
◯:過眠症は、夜間の睡眠はある程度休息機能を発揮しているにもかかわらず、日中に眠気や居眠りが生じる。ナルコレプシーという疾患では、発作的に強い眠気・居眠りが繰り返し生じる。
問6
✕:睡眠障害が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診する。
問7
✕:成人においては、おおよそ6〜8時間が適正な睡眠時間と考えられ、1日の睡眠時間が少なくとも6時間以上確保できるように努めることが推奨される。
問8
◯:日中に光を多く浴びることで夜間のメラトニン分泌量が増加し、体内時計が調節され、入眠が促進される。
問9
◯:閉塞性睡眠時無呼吸に関する説明として正しい。
問10
✕: 就寝前1時間以内の激しい運動は夜の眠りを妨げる可能性がある。就寝前はリラックスする時間を設ける方が良い。また就寝前の夜食や間食は、朝食の⽋食と同様に体内時計を後退させ、翌朝の睡眠休養感や主観的睡眠の質を低下させる。
問11
✕: たばこに含まれるニコチンは覚醒作用を有しており、睡眠前の喫煙は、入眠潜時の延長(寝つきの悪化)、中途覚醒の増加、睡眠効率の低下、深睡眠の減少をもたらす。
問12
◯:不眠症に関する説明として正しい。
問13
✕:平日の睡眠不足(睡眠負債)を、休日に取り戻そうと長い睡眠時間を確保する「寝だめ」の習慣は、実際には眠りを「ためる」ことはできない。
問14
✕:睡眠時間や就床時刻に過剰にこだわり、眠気が訪れていないにもかかわらず無理に眠ろうとすると、脳の興奮がむしろ高まり、寝つきを悪化させることがある。
◯:不眠症に関する説明として正しい。

キャリコンで睡眠について勉強するとは思わんかったわw
けどワイのイビキはうるさいらしいから、少しためになったで!
まとめ
この記事では過去問の傾向からピンポイントで作成しています。
ですので、一度は健康づくりのための睡眠ガイド2023の全体に目を通して置かれると良いかと思います。

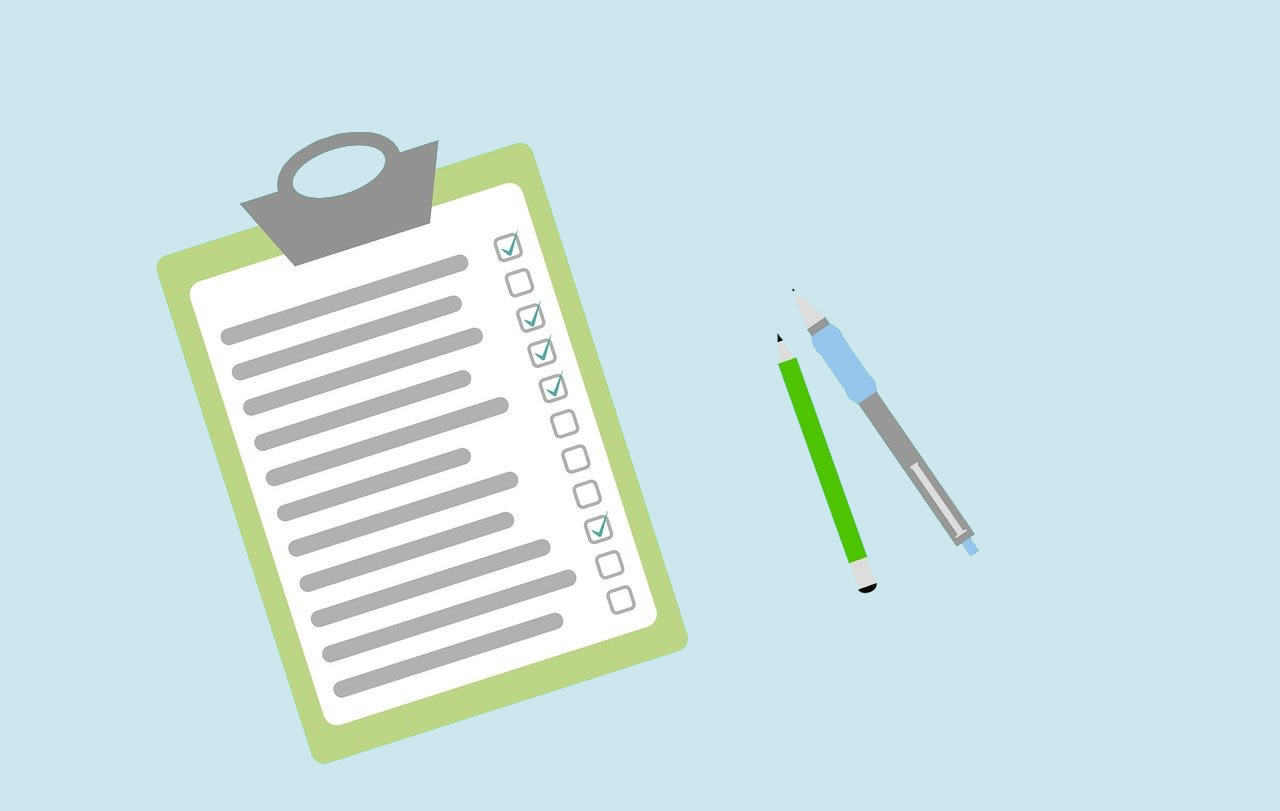
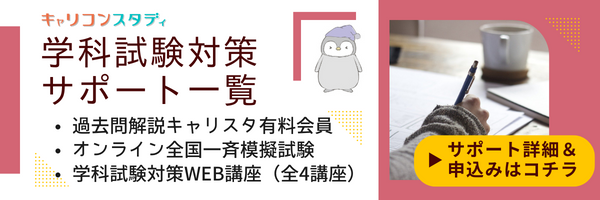
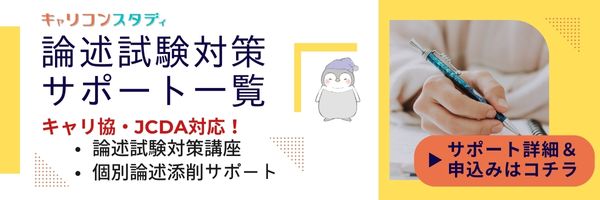
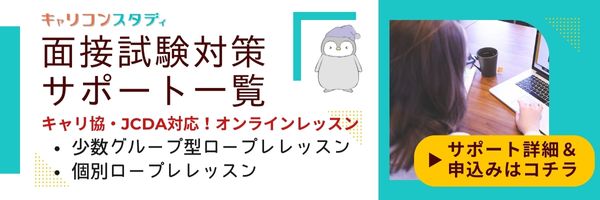


コメント