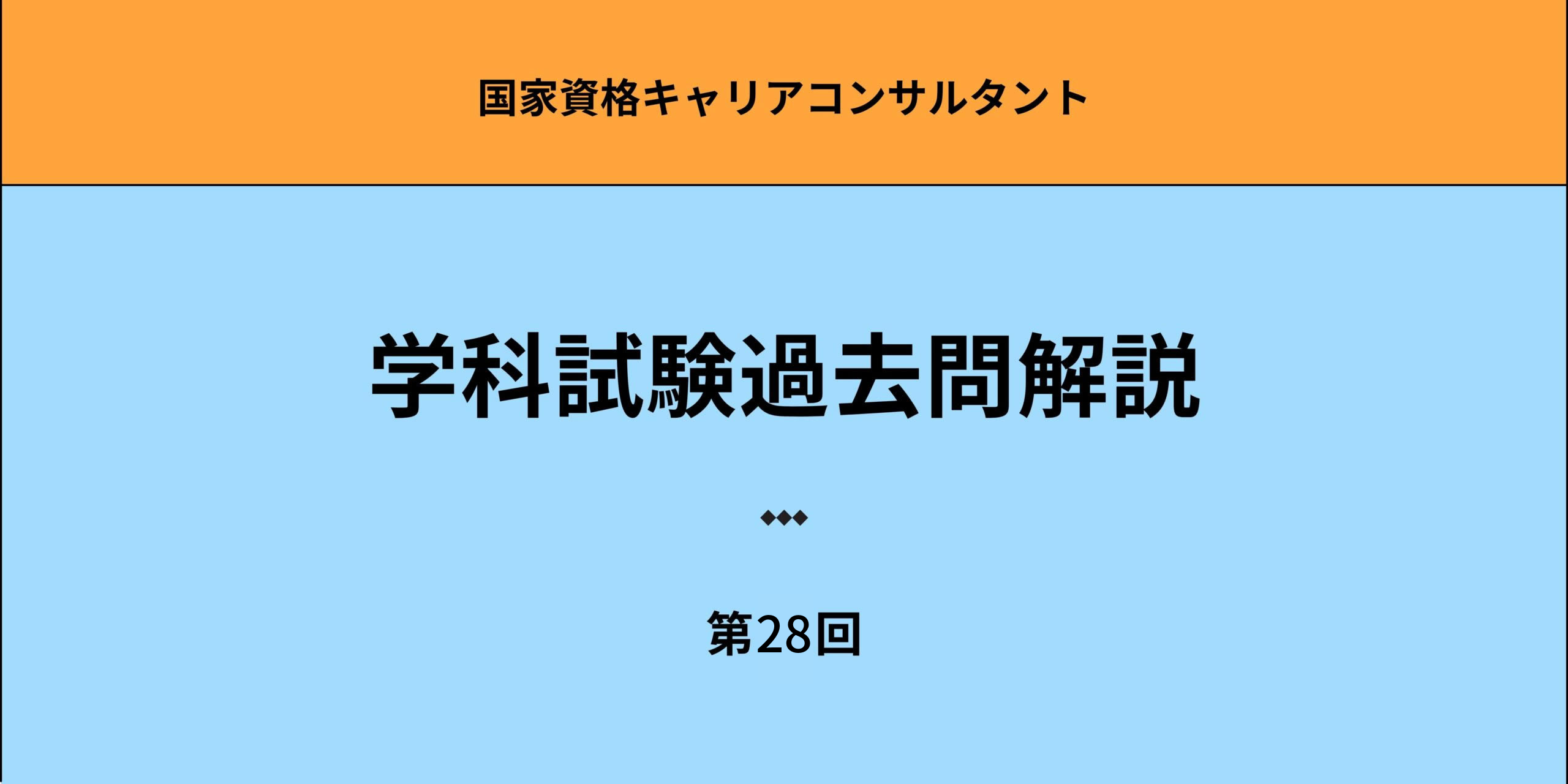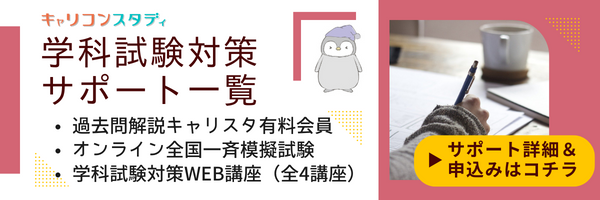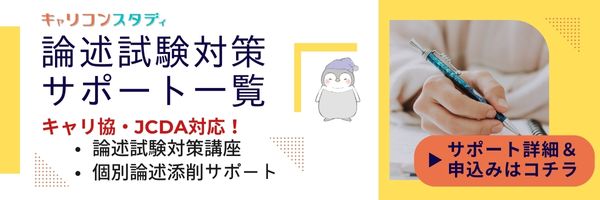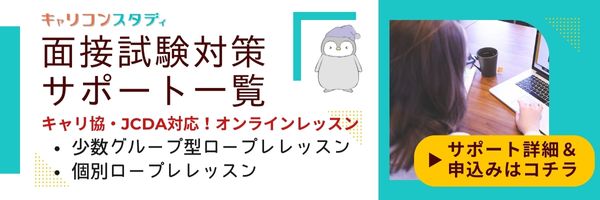このコンテンツは過去の学科試験の、
- 各問題の解説
- 各問題の正答
- 参考書籍・参考資料等
- キャリコンスタディ内の学習ページ
- 語呂合わせ
をまとめています。
解説には万全を尽くしていますが、万が一誤字・脱字や間違いがございましたらご指摘いただければと思います。
第28回学科試験 問1~問10の正答解説と参考元
問1
「令和5年版男女共同参画白書」(内閣府)で示された「令和モデル」に関する問題です。
正答:2
1.×:固定的性別役割分担を前提とした雇用慣行等は「昭和モデル」であり、「令和モデル」ではそこから切り替えるとしている。(P3)
2.〇:「令和モデル」の説明として正しい。(P109)
3.×:女性において優先的に実現するのではなく、男女ともに実現することが望ましい。(P6)
4.×:過剰な就労から女性を守るのではなく、女性の就労の壁となっている制度・慣行について見直しを進めていくことが必要である。(P109)
内閣府:男女共同参画白書

さぁ、28回の過去問!
解説で学んでいくでー!
問2
「令和5年雇用動向調査」(厚生労働省)で示された、令和5年1年間における就業形態別の労働移動者に関する問題です。
正答:2
1.×:一般労働者の入職率で最も高いのは「サービス業(他に分類されないもの)」である。
2.〇:一般労働者の離職率の説明として正しい。
3.×:パートタイム労働者の入職率で最も高いのは「生活関連サービス業、娯楽業」である。
4.×:パートタイム労働者の離職率で最も高いのは「生活関連サービス業、娯楽業」である。
厚生労働省:雇用動向調査
問3
「令和5年度能力開発基本調査 調査結果の概要(個人調査)」(厚生労働省)で示された、労働者のキャリアコンサルティング経験に関する問題です。
正答:3
1.×:令和4年度中にキャリアコンサルティングを受けた者は、「労働者全体」では10.8%であり、「正社員」では13.8%、「正社員以外」では5.4%であった。(P63)
2.×:キャリアに関する相談をする主な組織・機関は、「職場の上司・管理者」が最も多い。(P63)
3.〇:選択肢のとおり。(P63~64)
4.×:キャリアコンサルタントに相談したい内容は、正社員では「将来のキャリアプラン」が最も多い。(P66)
厚生労働省:能力開発基本調査
問4
サビカスの提唱するキャリア構築理論に関する問題です。
正答:3
1.〇:キャリア・アダプタビリティの説明として正しい。(P82)
2.〇:設問に関する説明として正しい。(P83)
3.×:「自分の内面にすでに存在する自己を実現する」という考え方を批判し、「クライエントは言葉を選んで自己を構成し、自己概念を形成する」としている。(P83)
4.〇:キャリア構築インタビューの説明として正しい。(P84)

設問1で、統制を『Control』と英語で書いてるのがなかなか意地悪やで!

問5
パーソンズの職業選択理論に関する問題です。
正答:2
1.×:スーパーのライフ・キャリア・レインボーに関する説明である。(P21)
2.〇:設問に関する説明として正しい。(P14)
3.×:クランボルツのプランド・ハップンスタンス理論に関する説明である。(P46)
4.×:文化に配慮したキャリアカウンセリングの説明である。(P67)

問6
ホールの理論に関する問題です。
正答:1
1.〇:選択肢のとおり。(P171)
2.×:自己志向的に変幻自在に対応していくキャリアと考えた。(P171)
3.×:プロティアン・キャリアは「自分は何をしたいのか」(=自己への気づき)を重視する。(P173)
4.×:プロティアン・キャリアを形成していくに当たって、必要な2つのメタ・コンピテンシーは、「アイデンティティ」と「アダプタビリティ」である。(P172)

ホールのプロティアン・キャリアは人気の理論やな!

問7
ホランドの理論に関する問題です。
正答:2
1.×: 8類型ではなく、6類型に整理した。個人と環境を同一の6類型にまとめ、個人と環境との類型が同一であることによって、調和的相互作用がより安定した職業選択、より高い職業達成などをもたらす。 (P67)
2.〇: 選択肢のとおり。(P68)
3.×:企業的職業領域は、企画・立案したり、組織の運営や経営等の仕事や活動の領域を指す。(P68)
4.×: 職業興味類型の関連性は距離で表現できる。隣にある領域は類似の興味を示し、対角線上にある領域は正反対の興味を示す。(P68)

問8
スーパーのライフステージと発達課題に関する問題です。
正答:2
1.×:人生全体の発達段階をマキシサイクルとしたとき、各年代のそれぞれに「成長」「探究」「確立」「維持」「離脱」のミニサイクルがある。(P73)
2.〇:設問に関する説明として正しい。(P72~73)
3.×:現実的な自己概念を持つことは、青年期(14~25歳)の成長段階の発達課題である。(P74)
4.×:他者との関わり方を学ぶことは、成人前期(25~45歳)の成長段階の発達課題である。(P74)
問9
動機づけに関する問題です。
正答:3
1.×:マズローは、欲求階層を基底層より①生理的欲求、②安全の欲求、③所属と愛情の欲求、④自尊と承認の欲求、⑤自己実現の欲求の5層から構成されるとした。(P23)
2.×:マクレランドは、強すぎる達成動機は自己実現を阻害するとしている。(P27)
3.〇:設問に関する説明として正しい。(P26)
4.×:ハーズバーグは、衛生要因が充分に満たされれば不満を予防するが満足はもたらさず、仕事への積極性を高めることもできないとした。(P26)
問10
マーシャが示したアイデンティティ・ステイタスの「アイデンティティ拡散」に関する問題です。
正答:4
1.×:「アイデンティティ達成」の説明である。
2.×:「予定アイデンティティ」の説明である。
3.×:「モラトリアム」の説明である。
4.〇:「アイデンティティ拡散」の説明として正しい。

アイデンティティの拡散は危機前、危機後という表現も特徴やな!