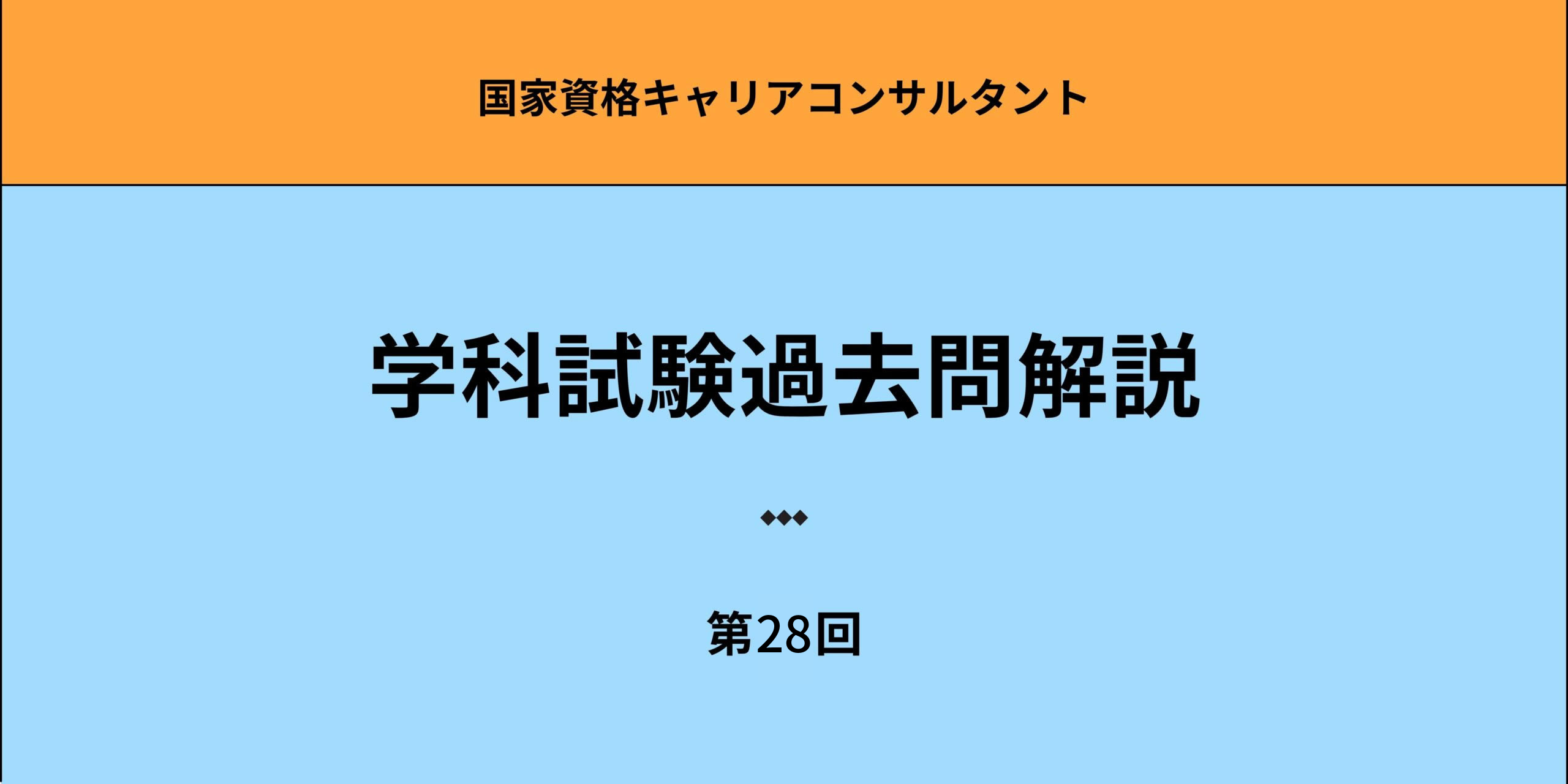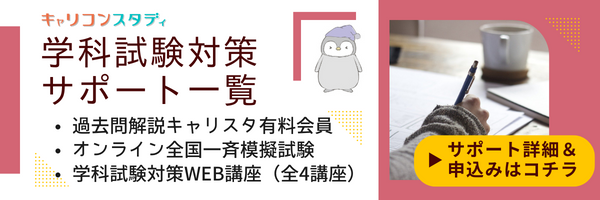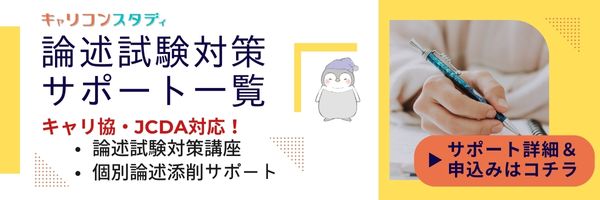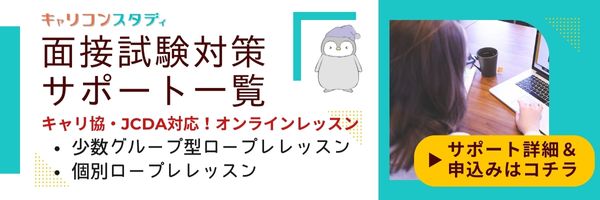このコンテンツは過去の学科試験の、
- 各問題の解説
- 各問題の正答
- 参考書籍・参考資料等
- キャリコンスタディ内の学習ページ
- 語呂合わせ
をまとめています。
解説には万全を尽くしていますが、万が一誤字・脱字や間違いがございましたらご指摘いただければと思います。
第28回学科試験 問41~問50の正答解説と参考元
問41
「職業理解・職業情報」に関する問題です。
正答:2
1.〇:選択肢のとおり。(P176)
参考:『キャリアコンサルティング理論と実際』6訂版:木村周、下村英雄
2.×:自分が属する世帯の家業に従事している家族従業者が行う仕事は、報酬を受けているかどうかにかかわらず、一定時間(例えば、一日平均2時間、あるいは通常の就業者の就業時間の3分の1以上の時間等)当該仕事に従事している場合には、その仕事を職業とみなす。
参考:日本標準職業分類(平成21年12月告示)一般原則(総務省)
3.〇:選択肢のとおり。
参考:統計基準等(総務省)
4.〇:設問に関する説明として正しい。(P2)
参考:第5回改定厚生労働省編職業分類の解説 まえがき(独立行政法人労働政策研究・研修機構)
問42
職業体験の意義に関する問題です。
正答:3
1.〇:設問に関する説明として正しい。
2.〇:設問に関する説明として正しい。
参考資料:トライアル雇用 (厚生労働省)
3.×:定年退職者よりも若い世代の方が働く意義の理解の促進に対して有効である。
参考:啓発的経験(厚生労働省)
4.〇:設問に関する説明として正しい。
問43
システマティック・アプローチの一般的な指針に関する問題です。
正答:1
1.×:まずクライエントとの心理的な関係を確立できなければならない。(P402)
2.〇:設問に関する説明として正しい。(P402)
3.〇:設問に関する説明として正しい。(P403)
4.〇:設問に関する説明として正しい。(P402)
問44
「将来、海外の大学院でマネジメントを学びたい」という目標を持つクライエント(大学生)への意思決定のプロセスでの対応に関する問題です。
正答:3
1.×:人は明確な目標を設定し、目標をもつことにより、目標を意識するようになる。このような意識変化は目標達成にむけた具体的な行動を促すことになる。(宮城:P168)
2.×:情報収集の原則は、クライエントが自分で情報を得る方法を教えることである。クライエント自身では情報収集が難しい場合は、情報そのものか情報の入手方法を教える場合もあるが、キャリアコンサルタントがその選択肢を絞ったり判断するべきではない。(6訂版:P387)
3.〇:説明文として正しい。(宮城:P170)
4.×:意思決定には、必ず「不確実性」が伴う。また決定されたことは変わることがある。意思決定は「完璧性」を求めるのではなく、複数の可能性を見いだすようにはげますことである。(6訂版:P388)
問45
方策の実行に関する問題です。
(第9回問40と全く同じ問題です。)
正答:4
1.×:来談者中心アプローチの説明文のため、適切でない。応用行動分析に基づくならば、気持ちの整理や考え方の変容ではなく、行動変容につながる介入を行う。(資料シリーズ№165:P123)
2.×:設問は指示的であり、クライエント中心療法とは言えない。(6訂版:P116)
3.×:過去の経験よりも未来のありたい姿に向けて検討するのは、精神分析理論とは言えない。精神分析的アプローチでは、キャリア選択や仕事への適応に関連する現在の行動と過去の経験を関連づけて考える。(資料シリーズ№165:P103)
4.〇:設問に関する説明として正しい。(6訂版:P117)
問46
方策の実行後の支援に関する問題です。
正答:3
1.×:目標設定の最終段階で、クライエントと一緒に努力したい意思をはっきりと伝えた上で方策の実行に移る。キャリアコンサルタントから進捗状況の確認を行うなど、一緒に目標に到達しようとするかかわりは必要である。(6訂版:P382~383、385)
2.×:目標は固定的なものではなく、変更可能である。内容を検討して別の支援を考えるなど、目標を変えることもある。(6訂版:P380、P385)
3.〇:設問に関する説明として正しい。(6訂版:P397)
4.×:将来、必要があればカウンセリングに戻ってこられるようにしておくと伝え、一定期間、一定の方法でクライエントをフォローする。(6訂版:P399)
問47
「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」(厚生労働省、令和4年6月)で示された、キャリアコンサルタントの推奨される取り組み例に関する問題です。
正答:1
1.〇:選択肢のとおり。
2.×:継続に支障をきたしている者には、より重点的にキャリアコンサルタントによる相談支援を行うことが推奨されている。
3.×:訓練されたキャリアコンサルタントに限定した活用ではなく、労働者が学び・学び直しを前向きに捉え直すような機会を設けるために、「ジョブクラフティング」の手法を援用することが推奨されている。
4.×:独自に推進するのではなく、企業と協働して支援策等の制度の改善を提案することが求められている。
「ジョブクラフティング」とは?
労働者が仕事の捉え方や意味づけなどを主体的に見直して仕事の充実感や満足度を高める手法のこと
問48
セルフ・キャリアドック実施後の結果や、結果を活かした環境への働きかけに関する問題です。
正答:2(BとC)
A.×:全体報告書には、個別の従業員が特定されないよう配慮した上で、面談対象者全体のキャリア意識の傾向や組織的な課題、及びその課題に対する解決策(提案)を盛り込む。(P12)
B.〇:設問に関する説明として正しい。(P25)
C.〇:設問に関する説明として正しい。(P24)
D.×:キャリアコンサルティング面談を通じて知り得た情報について、対象従業員の同意なしにキャリアコンサルタント自身以外の第三者に開示しないことを約束する「守秘義務」がある。(P19)
問49
キャリアコンサルタントが行う自己研鑽に関する問題です。
正答:3
1.〇:選択肢のとおり。(P1)
2.〇:設問の説明として正しい。(P4~5)
3.×:キャリアコンサルタントとしてのキャリアの初期段階にある者に留まらず、経験を積んだキャリアコンサルタントにおいても、積極的かつ定期的にスーパービジョンを受けるべきである。(P7)
4.〇:選択肢のとおり。(P1)
問50
キャリアコンサルティングにおける多重関係に関する問題です。
正答:3
1.〇:設問に関する説明として正しい。
2.〇:設問に関する説明として正しい。
3.×:多重関係があるからこそ、クライエント側の自己開示がしづらくなる可能性もある。
4.〇:設問に関する説明として正しい。

28回過去問、お疲れさまやでー!
出来はどうやったかな?試験まで時間はあるからしっかり苦手を克服していこうな!